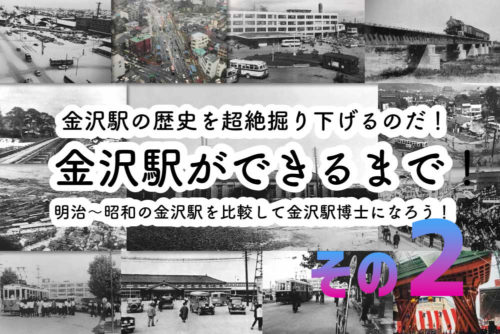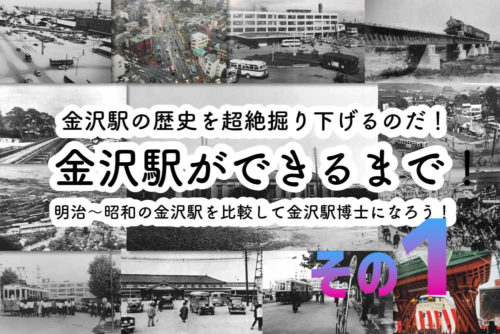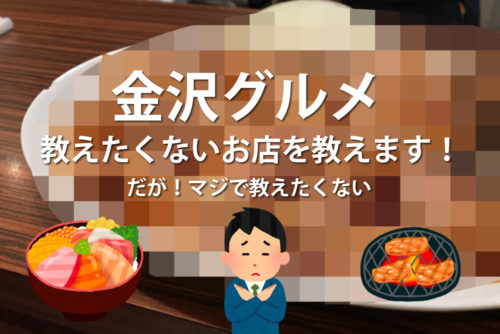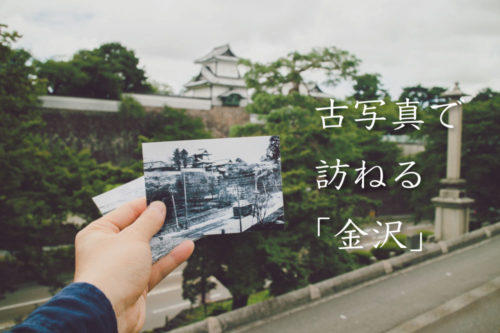【趣膳食彩2017】「金沢の究極の食と工芸と文化」を楽しむイベント!2017年10月14日は是非とも参加ください!
金沢と言ったらやはり食。そして、その食を彩る工芸、文化。それらを凝縮したイベントがこの趣膳食彩です。言い換えればこのイベントは
趣のあるこの名前にふさわしいイベントです。2017年10月より順次開催されます。
趣膳食彩は2010年より金沢青年会議所(金沢JC)が中心となり「かなざわ燈涼会 趣膳食彩」として始まりました。趣膳食彩は今年で7年目となります。北陸新幹線の開通が2015年でしたのでその5年も前から趣膳食彩は行われていました。現在ではその金沢青年会議所(金沢JC)から中心は趣都金澤(しゅとかなざわ)が中心となってイベントを開催しており年々進化を遂げているイベントとなっています。
今年2017年の趣膳食彩ではなんと、本マガジンの編集長である私もディレクションさせていただいております。それが
「梅田日記」とともに
幕末の金澤をめぐる
「梅田日記とともに幕末の金澤をめぐる」 は多少こ難しい感じの内容となっていますが、これこそ金沢の奥深さだと考えています。分かる人だけが分かるではやはり意味が無い。現代とリンクすることで時空を超え昔を生きているように感じる。本マガジンでもそのように心がけているのですが、その位の案配がちょうどいいのでは無いかと思います。
梅田日記とは
と思いますが、この梅田日記。幕末の金沢の詳細を記した貴重な町人の日記なのです。この「梅田日記」は天保4年(1833年)西御坊町生まれた梅田甚三久(うめだじんさく)が金沢での普段の生活を記した非常に貴重な幕末の日記。日記の一部は行方不明であるが、激動の幕末の金沢の様子、暮らしを克明に記録してあり、金沢での暮らし、街の雰囲気すら伝わってくる。元治の変(げんじのへん)、卯辰山開拓、大政奉還などの金沢の雰囲気なども記録されている。というものなのです。
便利な時代で、梅田日記は実はAmazonでも購入ができます。
地方・小出版流通センター
売り上げランキング: 1,601,790
講師などのご紹介
今回のイベント「「梅田日記」とともに幕末の金澤をめぐる」の講師などをちょっとご紹介したいと思います。
梅田日記」町歩き担当 武野 一雄

金沢の観光ボランティアガイド「まいどさん」メンバー。 その知識の深さから「金沢の伝説のガイド」と呼ばれ ている。ブログ「市民が見つける金沢再発見」も運営。
「梅田日記」座学担当 竹松 幸香
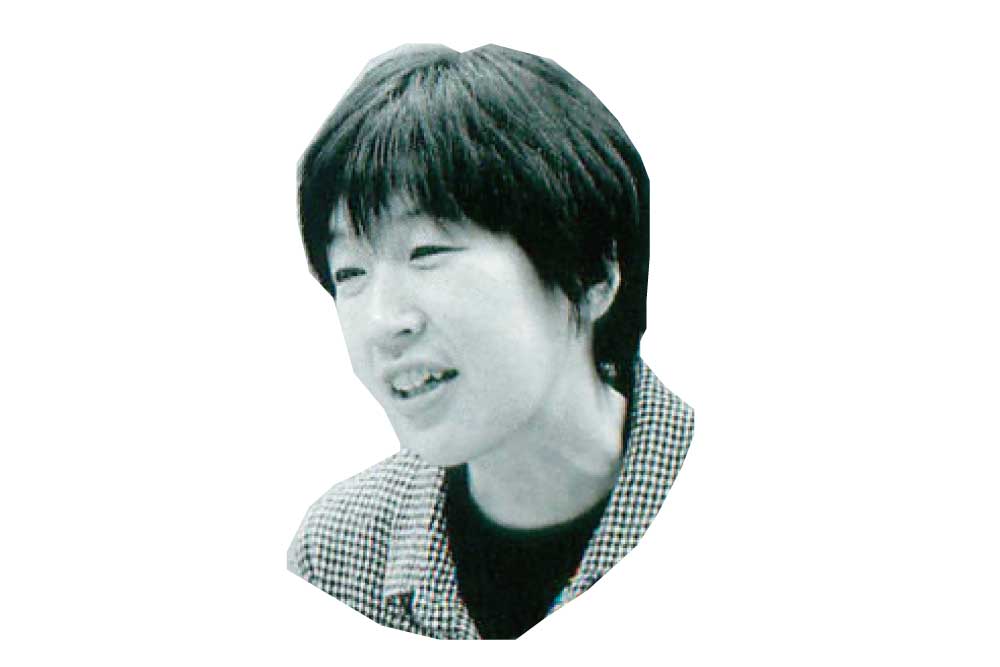
富山大学大学院、金沢大学大学院を経て、2002年 より前田土佐守家資料館学芸員。2016年7月には 「近世金沢の出版」桂書房より出版。博士(文学)。
竹松 幸香さんの著書はAmazonでも購入が可能です。
陶芸 吉村 安司

金沢市出身、京都嵯峨美術短期大学 陶芸卒業、京都精華大学 陶芸卒業、金沢市卯辰山工芸工房修了、展覧会多数
展覧会の合間は、料理屋店からの注文を多く手掛ける。地元の土でカタチをつくり、果樹の灰で色を出すことが楽しくてやきものを続けています。この素材で出来ることをこれからの可能性と信じ新しい作品を生み出していきたいと考えております。
鮨くら竹 倉橋 晃規

白山市出身。19歳から東京の寿し店などで研鑽を積み、帰郷後は金沢東山の「鮨みつ川」で修業。「鮨歴々」百番街店の店長としても活躍。鮨くら竹の情報はこちらより。
クリエイター 小西裕太

北陸先端科学技術大学院大学(修士課程)修了。自然の音を配信するGoogle公認のYouTuber。2008年より都内ITベンチャー企業取締役として勤務後、石川の郷土愛が講じその魅力を伝えるWebマガジン「ビューティーホクリク」を制作・運営。ビューティーホクリクはこのサイトです。
イベントの流れ
この実際の日記の舞台はひがし茶屋周辺ということで梅田日記とともにこのひがし茶屋周辺を町歩きするのです。町歩きの後にはひがし茶屋を眺めながらみんなで金沢の鮨を満喫します。

2. 「梅田日記」に登場する場所を実際に町歩き (武野 一雄さん)
3. 宝泉寺でひがし茶屋を眺め、鮨を食べる (鮨 倉橋 晃規さん、陶芸 吉村 安司さん)
陶芸の土はこの宝泉寺周辺の土を使用!
食べておいしい、知っておいしい。最高のイベントとなると思います。是非とも参加していただけると本マガジンも喜びます。どうぞよろしくお願いします。